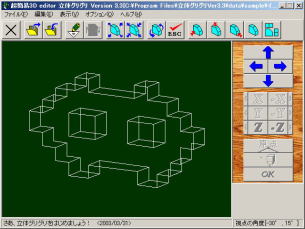 製図の授業 計8時間 1.伝言ゲーム(製図の役割) 1時間 2.キャビネット図 1時間 3.等角図 1時間 4.正投影図 1時間 5.立体グリグリ操作実習 1時間 6.立体グリグリ作品作成 2時間 7.まとめ 1時間 |
1998/08/03
立体グリグリを使ってみて
1.はじめに
川俣・平田両氏によって「立体グリグリ」が Windows版としてバージョンアップされてきた。「立体グリグリ」は簡便な操作で楽しみながら立体の概念を養うことが可能な優れたソフトである。
ここではこの新版ソフトを今年度授業で使用したのでその様子を報告する。
2.生徒の様子
本校は八ヶ岳の麓、標高1000mにある高原野菜とペンションの村である。生徒も比較的素直で技術の授業にも積極的な生徒が多い。1学年は3クラスで各クラス32名〜33名である。
3.製図の授業の流れ
本校では製図は1学年の木材加工の前半8時間を使っている。製図学習の流れは以下のようである。個々の内容にかける時間は十分とはいえないが、全体の時間数が少ない現状では仕方ないと考えている。
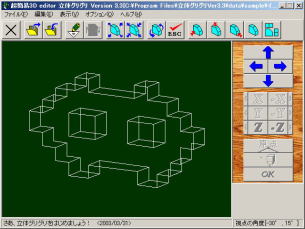 製図の授業 計8時間 1.伝言ゲーム(製図の役割) 1時間 2.キャビネット図 1時間 3.等角図 1時間 4.正投影図 1時間 5.立体グリグリ操作実習 1時間 6.立体グリグリ作品作成 2時間 7.まとめ 1時間 |
4.授業の様子
(1)コンピュータ環境
本校は2年前にWindows機に入れ替えてネットワーク化し、ホームページ作成やインターネット、ドリル学習、各種ソフトなど様々な形で利用されている。休み時間や昼休みは生徒に自由に開放している。
コンピュータ室は生徒機はNECのCx13(P133・47MB)20台とV12(P133・32MB)20台の計40台でNTサーバーを中心にネットワークが組まれており、サーバーのデータを個々の生徒機で共有可能である。「立体グリグリ」は個々の生徒機に入れたが、セットアップのファイルはサーバーに置くことでFDを持ち歩かなくても設定ができた。「立体グリグリ」はVer3.0を使用した。
(2)「立体グリグリ」操作実習(1時間目)
他の教科でドリルなどでも使っているため、Windowsの操作自体はできる生徒が多いが、立ち上げからグリグリを使うまでを説明し、大型テレビに投影し説明した。立体を呼び出して回転させると「おー」「カッコイイ」といった声が次々に起き、意欲を持ったようであった。個々の操作に移ったが、操作でつまずく生徒はあまりおらず、サンプルを呼び出しては動かして試すことができた。数多くのサンプル、特にハイレベルな作品を見ると動かしながら「すごい〜」「面白い〜」という声が出ていた。今の生徒は3DのCGはテレビやゲームなどでなじみがあるが、自分でも作れる、ということは驚きであったようだ。見ながらも「どうやったら作れるの?」「早く作ろうよ」と制作に興味を持つ生徒が多かった。
時間の後半を使い、作図の仕方を伝えた。縦横高さ(XYZ軸)という3次元の考え方、キーの操作を確認した後、自由に線を引いたり消して作った物を動かして見るようにした。すぐに書き出せた生徒は3分の1ほど。他の生徒には回りながらキー操作など指導して回った。やはり作図は抵抗感があったが、できたものがその場で動かせるというので熱心に動かしていた。15分ほどで数名の生徒はサイコロとか簡単なアルファベットなどを作ることができていた。次回本格的に作品を作ること、作品の構想を考えておくことを伝えて終えた。生活記録でも「とても楽しかったです。早く作りたい」と書いてきた生徒が多かったようである。
(3)「立体グリグリ」作成実習(2・3時間目)
2時間目は操作の確認をしてから制作のポイントを伝えた。1時間目の様子から直感的に操作できる生徒はそのまま作品が作れるが、XYZ軸の感覚が分からない生徒は線を引けても自分の願う立体を作成はできない。そこで以下のような指導をした。
①作図モードにしてから正面へ移動する(XY軸のみ見えるZ軸は奥行きとなる)
②XY軸で立体の正面図にあたる部分を書く(お絵かきソフトの感覚)
③等角図にしてZ軸へ線を延ばし、奥行きを決める
④奥行きを固定して再び正面へ移動(XY軸のみの形)
⑤Z=0の位置に書いた図に重ねるようにして書いていく
⑥多少回転させ、奥行きをつないでいき、完成
以上の手順を踏むことでほとんどの生徒が2時間で作品の完成をすることができた。流れとしては平面の形に奥行きをつけていく、という流れで作品のパーターンもロゴなどが多くなり、固定されがちだが、課題をステップ式に学習していく時間がない中では作品を完成させるには有効な方法であった。画面を前に「うーん」とうなっている生徒、どんどん作成していく生徒など様々であるが、集中が切れている生徒は一人もいなかった。
20分もすると数人が形になり、ロゴなど完成させた生徒も出てきたので保存の仕方を伝えた。合間を見て形になった生徒の作品を全体に提示するとさらに意欲が高まってきた。またこの間に操作が分からないと教え合おう、という話をしていたが、隣などで聞き合いながら操作する姿も見られた。2時間目の終わりには3分の1ほどの生徒が立体を作り上げ、大半の生徒が何らかの立体を作れるようになった。
休み時間にそれぞれの作品を見て回り、相互に「いいなあ」「うまいね」「私の見て」と評価し合う姿も見られた。ただ1時間の集中でかなり疲れも出たようである。それだけ集中して制作したのであろう
3時間目はさらに仕上げで完成させ、後半で作品のホームページ化を行った。
(4)作品のホームページ化(3時間目)
本校では外の学校HPとは別に校内ネットワーク上で校内だけのホームページを設定している。各教科、クラブ、部活、クラス、学年、個人といった幅広い内容のホームページが開設され、校内どこからでも自由に見れるようになっている。この個人ページを利用して「立体グリグリ」で作った作品を画像データとしてページに張りつけ、相互の見れるようにした。
ホームページ化はブラウザ(ホームページを見るソフト)であるインターネットエクスプローラ4.0に付属のホームページエディタを使用した。「立体グリグリ」にある「コピー」という機能で自分の作品を一番いい角度でクリップボードにコピーする。クリップボードを経由して付属のホームページエディタを立ち上げ、自分のホームページに画像をコピーし、コメントなど入れて更新すれば完成である。
3時間目後半にやり方を説明し、完成した生徒からページ化していった。早い生徒は2作品完成させた生徒もいた。しかし4分の1ほどの生徒は作品をぎりぎり完成させるのが精一杯でページ化は休み時間を使って行った。
ページ化を伝えたことで生徒の意欲をさらに高めることができた。その中で短時間で各クラス高いレベルの作品を完成させた生徒が出てきた。
授業では感想を書いている時間がとれなかったが、「難しかったけどうまくできて良かった」「大変。疲れた〜でも面白かった」「面白かった。もっと作品を作りたい」という声があった。抵抗感もああるが、完成できた喜びは大きいようである。
完成後のページはプリントアウトして技術室に掲示したり、休み時間に見合えるようにした。特に「ワニ」「車」などの素晴らしい作品には感心する姿が見られた。次の時間に透明モデルで立体のまとめも行ったが実物の立体もグリグリのように動かしてみている生徒が多かった。
5.実践を終えて
Win版「立体グリグリ」を使用してみて以下のように感じ取れた良い点
・立体を自由にいろいろな角度から見ることで一定の立体感覚を養えた
・生徒の興味、関心を引きつけ、製図に意欲を持たせることができた
・平面からおこしていくことでほとんどの生徒が作品を完成できた
・DOS版に比べ操作が簡単になり、基本操作でつまずく生徒がいなくなった
・ホームページ化などデータの二次的な加工も簡単にできるようになった
6.今後の課題
・より段階的な作図指導の研究
・マウスなどより簡便な作図方式の改良
・現実の3Dや製図など実際の技術への橋渡しをより充実させる
もう少し時間を取れればさらに質の高い作品を完成することができたが、短時間でこれだけの作品ができたことは良かった。このような優れたソフトを開発していただいた川俣・平田両氏には深く感謝したい。
長野県原村立原中学校 村松 浩幸